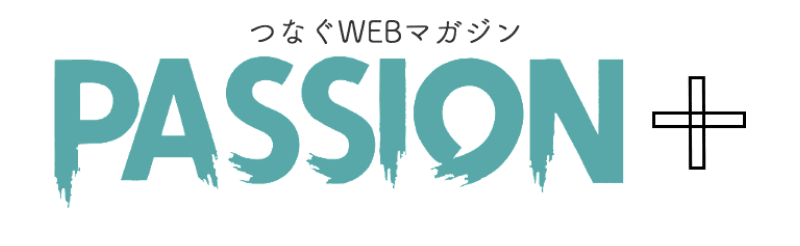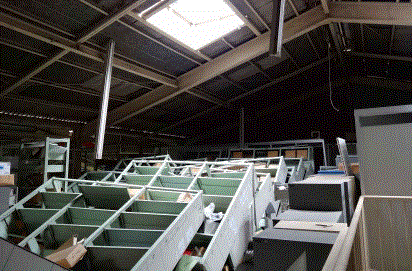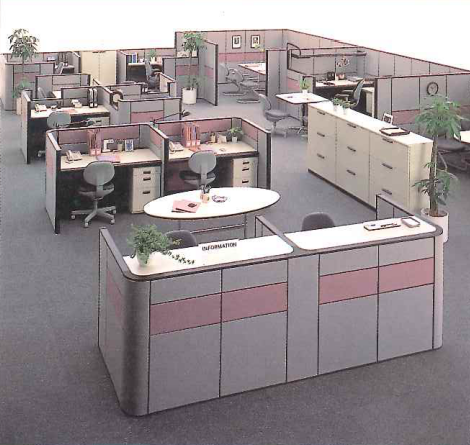COMPANY
設備メーカー、IPMとの出会い
はじめに筆者が所属する金剛株式会社(以下、金剛)は、博物館・美術館の収蔵庫設備及び展示設備、図書館家具及び書庫設備といった保存、保管設備全般の設計・製作・施工・メンテナンスを一貫した実施体制を有するメーカーです。
私ども金剛がまずIPMを知り、IPMに携わるきっかけとなったのは、平成17(2005)年の九州国立博物館(以下、九博)の収蔵庫工事があげられます。九博設立準備室のご指導の下、収蔵庫設備の建築段階よりIPM活動を取り入れた製作・施工はこれまでにはない考え方で進みました。特に、設備の設計仕様をはじめ、材料選定とトレーサビリティによる品質管理、虫・カビの温床となるものを持ち込まない工事現場の衛生管理、工事中の清掃作業等においてもIPM的活動の意識づけが行われ、施工を通じた文化財保護のための知識や配慮の重要性を本工事に携わった社員関係者は学ぶことができました。

さて、筆者は主に営業支援・販売促進、製品企画等の業務を担当しており、残念ながら九博工事に携わっていません。納入後、販売促進用の写真撮影での訪問が初めてでした。表敬訪問へ帯同した時、副館長、担当課長より「収蔵庫は作るだけでは終わらない、IPM的収蔵庫のメンテナンスについては、収蔵庫メーカーの役割も重要になってきた。」とのご意見を頂き、企画担当としてビジネスプランの立案に着手しました。
机上の論理とよく言われますが、IPMという言葉だけでは正直分かりづらい所があり、まずは九博におけるIPM活動の見学をはじめ、IPM研修会やIPMシンポジウムといった知識向上のための学ぶ機会に積極的に参加していきました。当初はIPMに関するテクニック論を求めていたのですが、関係の方々と話を重ねるうちに、大切なものを伝承するための「理念」を学ぶことに至りました。
文化財IPMの理念
文化財IPMの経緯や内容については、多くの有識の先生方にて報告があるので筆者からの詳細は割愛します。文化財IPMに関して筆者の認識としては、「従来の薬剤駆除の定期実施の保存管理」から「IPM活動といった人の目と計測データによる日常管理の保存管理」へ、管理手法やその考え方がパラダイムシフトしたと考えています。
具体的には、パラダイムシフトの1つ目として、これまでは担当学芸員と専門技術者によって文化財保護のための知識や配慮が行われてきたと思われますが、IPM活動の場合は、担当学芸員だけでなく総務職員や清掃員、警備、市民ボランティア、PCO会社、物搬会社、さらには私どものようなメーカーまでが携わり、多くの方々が協力して文化財保護の一端を担うことになるのです。文化財保護のための知識や配慮の「共有」と力を合わせて事に当たる「協同」こそ、文化財IPMの理念だと考えています。文化財IPMが単に掃除だとか、温湿度計による情報収集の単なるツールだけではなく、協同してある1つの目標に向かって進む、組織を変革するようなパワーを持っていると感じています。実際、九博のIPM支援者研修報告会では、参加者の活き活きした発表内容と意気込みのある顔つきを多く見てきましたので、確信に近いものと感じています。
パラダイムシフトのもう1つが、設備(ハード)ありき論や業者依存論からの脱却であり、日常活動(ソフト)を含めたIPM的起点の協同ソリューションです。私どもは、メーカーとして設備による最適な保存環境管理をサポートしてきましたが、限界があることも事実です。
例1)停電や節電に伴う空調設備の停止 (実際はランニングコストの低減、運営予算の圧縮)
例2)施設建屋や設備の老朽化 (改修費用が多額で予算獲得が困難)
例3)収蔵庫や書庫の狭隘化で空調の排気口が塞がっていた (空気循環の停滞が発生)
上記の要因で温度、湿度の変化が生じたことによる生物被害の話もよく聞くところです。また既存施設の建材や梱包資材による影響も文化財保存修復学会等でも報告されています。これからはエンドユーザー様と業者とが協同でこれらの要因を把握することで、施設全体の危機管理の掌握にも繋がっていくと考えています。
上記のパラダイムシフトは正直、全国的に広がっているかは判断が難しい所ではありますが、筆者が接するエンドユーザー様には着実に広がっていると感じています。
維持管理・IPMメンテナンスの必然性
80~90年代はいわば博物館・美術館のベビーブームでもあったため、現在、施設の老朽化は言うまでもなく、それと同様に「保存環境」「収納能力」のことで頭を抱えている館も多くあるとお聞きします。
一方で最近、老朽化したインフラや公共施設で発生した事故(例えばトンネル天井崩落事故)は、記憶に新しいところです。これらの多くの課題は、維持管理が後手に回されたり、点検を軽視したことによる結果だと思われます。
モノづくりの現場では、特に工場設備の定期点検についても人手を割いて実施され、点検に携わる人材の育成が行われています。点検で異常が見つかれば、早めに対処する「予防保全」に取り組むことが大事です。状況が悪化してから直す「事後保全」に比べて費用が抑えられ、設備の寿命を延ばすことができます。
上記の背景を踏まえながら、近年、新築や改修にて素晴らしい保存設備や展示設備を大規模な予算を執行して作り上げられた施設は、それを適切に維持管理していく必要があると考えます。メーカーとしてハードとソフトを融合した提案で、総合的なソリューションをご提示できるように経験と工夫を積み上げて参りたいと考えます。
メーカーの立場でのIPMコーディネータ
金剛では設備提案(ハード)だけでなく、資料保存活動(ソフト)まで多岐に亘り、お客様からの相談対応が増えています。IPM活動も含めた総合的サポートによるお客様ソリューションの実践で、現在、納入後のメンテナンスとして、エンドユーザー様との協同でIPMメンテナンスのサポートを行っています。
また、モノづくりにも積極的に反映させていくことで、使い勝手のいい、メンテナンス性のいい製品の開発や改善改良活動へ取り組んでいます。
例1) 収納棚の場合、これまで収納量を重視した設計仕様でしたが、掃除し易いように掃き足仕様を社内標準としました。これは古くから床の最下段には何も置かないという先人の知恵にも通じるところがあります。
例2) 館内内装工事は建築工事のカテゴリーに入ります。内装工事は段階的に清浄度を高めるように清掃を計画していきます。最終引渡し前には専用クリーナーと専用クロスにて、カビの温床となる収蔵庫内の塵埃の除去に努めています。
例3) 収蔵庫に什器をレイアウト提案する場合も、空気の停滞する空間や埃溜まりがないように設計考慮しています。しかしながら慢性的な収納空間不足を抱える施設では収納力(能力)を重視されがちであり、安全の基準をどのように設け、お客様とのコンセンサスを図ることに関してはこれからの課題と思っています。
結び
筆者はIPMを学び始めて、「気づき」と「意識の変化」を感じています。
気づきというのは、IPM研修会の実習の中で塵埃の話が出てきますが、結構、部屋にも埃溜りがあり、毎週末それを掃除機で吸い取ると、その塵埃の多さにびっくりします。掃除を重ねるうちに埃溜りの場所がある程度、特定できるようになりました。大抵は隅にあるのですが、机のちょっとした溝の中とか、普段は全然気づかない、意識もしなかった所にも気づきが生まれたことは大きな収穫です。これは施設でも同様だと思います。
意識の変化については、他の人に任せずに自分自身で動いて、やってみことで、筆者自身の意識の変化に繋がりました。文化財IPMという言葉だけでは難しそうですが、自分自身がやってみことで、色々な面で学ぶことができました。筆者は博物館や美術館、図書館に勤めているわけではありませんが、現在の業務や私生活を通じて、文化財IPMに繋がる考え方を経験していると思います。今後は、さらに全国の多くの施設を通じて経験を積み、適切な提案を発信できる「収蔵庫メーカーのIPMコーディネータ」として、文化施設におけるIPM活動をサポートして参りたいと考えます。
IPMの視点からメーカーとしての責任はどのようなものなのか、文化財IPMコーディネータをどう活用していくのかと現在も試行錯誤しています。まだまだ、整理は未成熟な状況ではありますが、今後、エンドユーザー様をはじめ、PCO会社、物搬会社との連携を行い、メーカーとしての情報収集と経験を蓄積していくことが課題です。
さらにそれらの経験や工夫を社内外へ発信していき、より綿密なコミュニケーションを図りながら、文化財IPMの理念をはじめ、よりよい保存環境への貢献、さらに私どもの企業理念である「安心と先進で、社会文化に貢献する」を探求していきたいと考えています。
文:木本 拓郎 (金剛株式会社 業務本部)
※取材当時
(2013年10月)