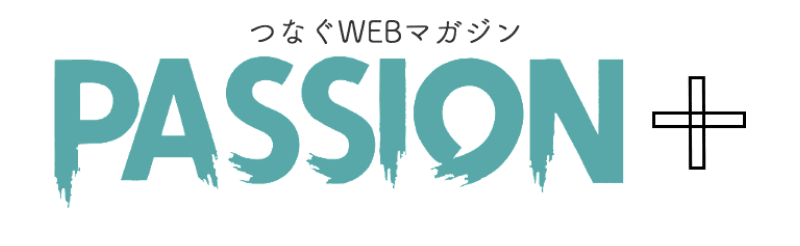COMPANY
話し手(写真左から)
白濱 香織 熊本市立城南図書館司書・サブリーダー
津村 秀夫 熊本市立城南図書館館長
北嶋千夏 熊本市立城南図書館司書・リーダー
聞き手
矢賀部仁 金剛株式会社 社長室
※所属・役職は取材当時のものです。


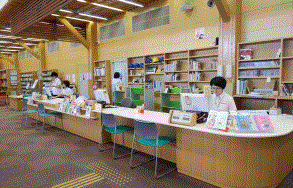

―熊本地震は二度にわたる大きな揺れがあったのが特徴でした。発災当時の状況について教えていただけますか。
今回の地震は、前震(4月14日)、本震(同16日)ともに図書館が閉館した後の夜間に起きた地震でした。熊本の公共図書館はほぼ同じだと思いますが、利用者の避難誘導などの心配をせずに済んだのは幸いだったと思います 。前震後の惨状を目の当たりにしたのは翌日4月15日の朝でした 。もちろん本は散乱していて、天井に設置されていたガラス製の防煙垂れ壁が落下して破片が飛び散っていました 。床に落ちた本は通路を確保するために床に積み上げ、ガラス片を巻き込んだ本は別室へ移動しました 。その日はほとんどの職員が出勤することができましたので、かなりのペースで作業を進められました 。パソコンはカウンターに設置していたものが1台倒れていましたが、事務室のものは全台が無事でした 。


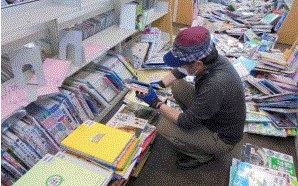
―その夜、1時25分に本震が起きました。
本震後に館内の状況を確認できたのは16日の朝でした 。予想はしていましたが、15日の作業も虚しく被害は拡大していました 。特に酷かったのは新書コーナーが隣接する館内西側の壁の損壊でした 。外からの風雨が懸念されるほどに隙間が広がってしまっていました 。余震も続いていましたので、職員の安全を確保するために、予定していた作業は基本的に中止にしました 。ただ、二次被害を拡大させないために館長はじめ少数の職員で、損壊した壁の本を壁から離してブルーシートをかぶせる作業だけは行いました 。当時は道路が大変渋滞していましたし、ガスや水道といったライフラインも満足な状態ではなかったので、18日までは全作業を中断しました 。一部の職員だけで作業を再開できたのは19日のことでした
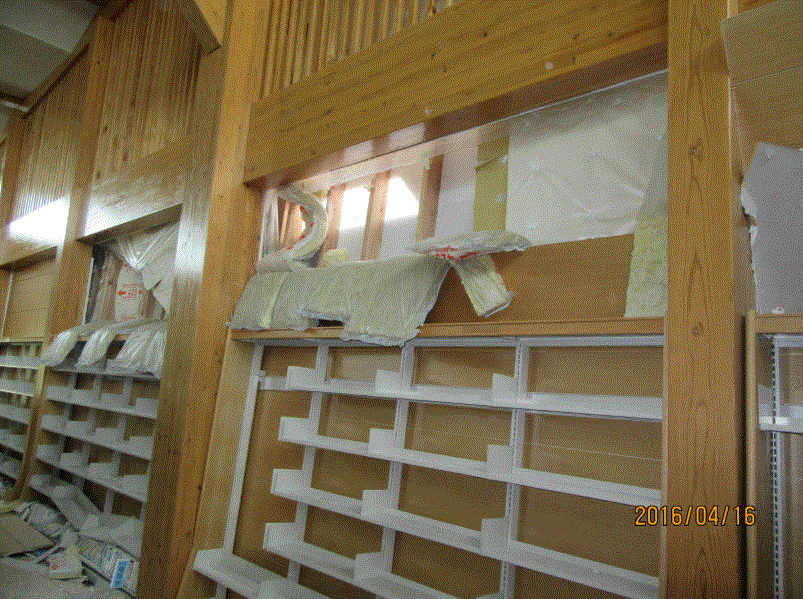

―19日の時点でも余震がかなり頻発していたので、やはり安全面での心配はあったのではないでしょうか。
とにかく職員の身の安全が第一ですから、全員にヘルメットを着用させました 。床に落ちた本は一冊ずつキレイに拭き、割れたガラスを巻き込んだ本は1ページずつ確認しながら刷毛で丁寧に破片を払い落としました 。手間のかかる作業でしたが、これらは職員の自発的な提案によるものでした 。自身の安全確保をしながらも、開館後に利用者の方が安心して利用できるようにという配慮は忘れずに作業をしてくれました 。
―ガラス片の除去は大変でしたね。そもそも天井のガラス製の防煙垂れ壁が落下したということでしたが。
この建物は天井が高く、普段は視界に入らないため、頭上にそういうものがあることを知りませんでした 。最初、ガラスが割れているという一報を受けた時も窓ガラスか何かだと思っていたのですが、窓ガラスはどこも割れてないし、不思議に思っていたぐらいです 。落下してきたガラス片で、カウンターのパソコンのケーブルは見事に切れてしまいました 。木製書架の天板には、今でもその傷跡が生々しく残っています 。利用者がいる時間帯だったらと思うと本当にゾッとします 。現在は防煙垂れ壁の下には注意喚起の掲示をしています 。最近は防煙垂れ壁もグラスファイバー製のものなど、割れない素材のものが注目されているようですので、図書館でもそういったものを導入していく流れになるのではないでしょうか 。
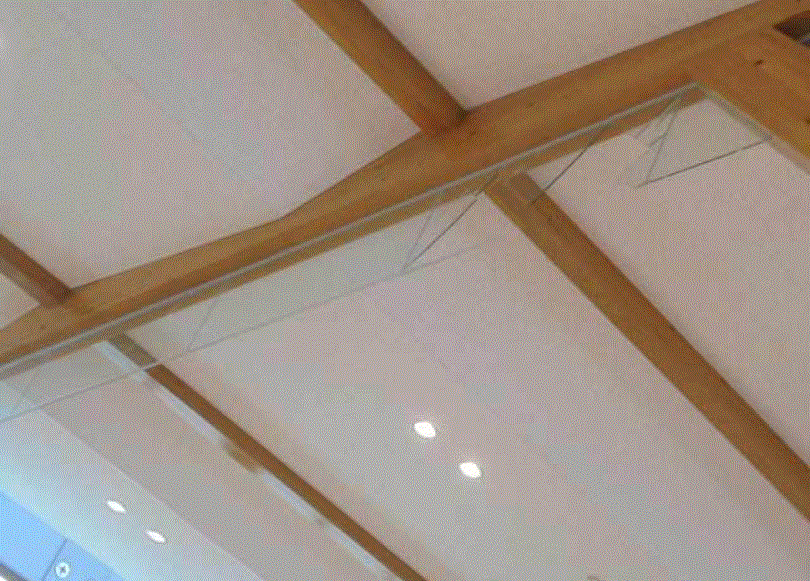
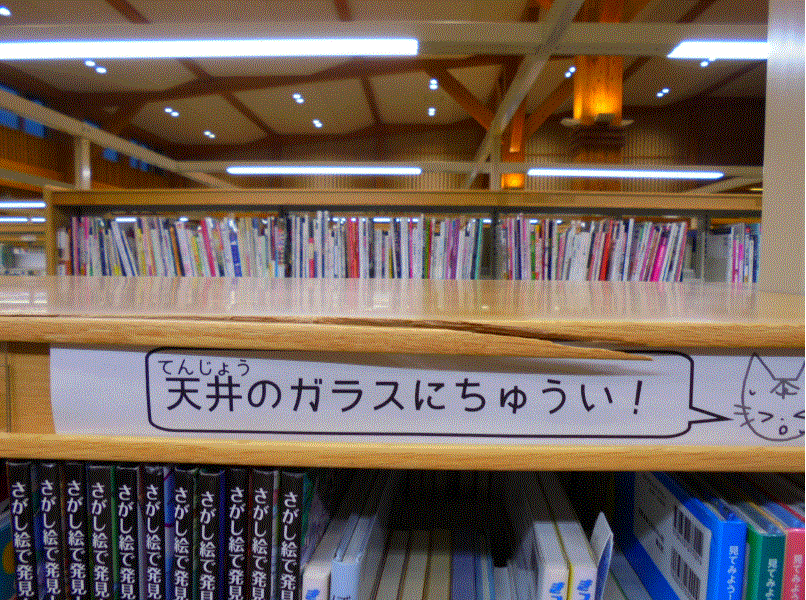
―当時は職員の皆さんも、まだご自身の生活もままならない中でしたよね?
当初作業に参加できたのは半数ぐらいだったでしょうか 。ご家族で避難所に身を寄せていたり、車中泊を続けている職員もいたので、やはり作業にあたることができた職員は限られていました 。出て来られた職員の中でも、終日作業できる者、半日だけ作業できる者など事情は様々でした 。それでも無理しない範囲でみんなで協力しあいながら、いろんな作業を分担して手際よく進めてくれました 。
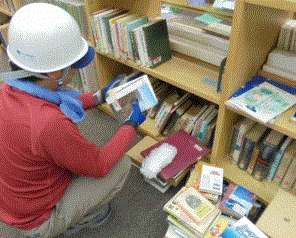
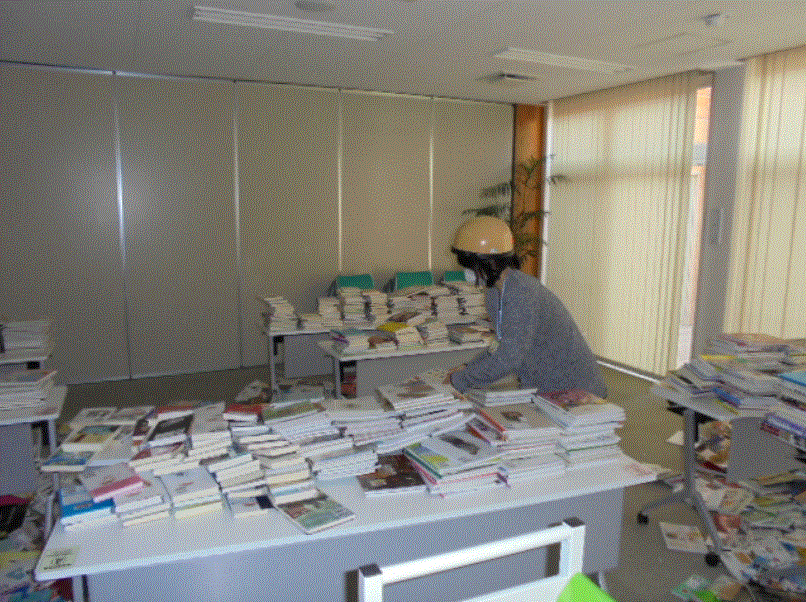
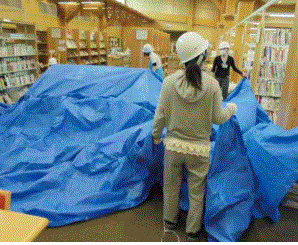

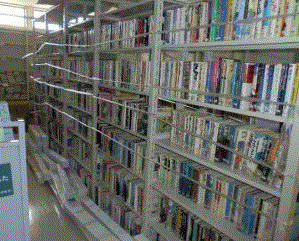
一段ずつビニール紐を張った
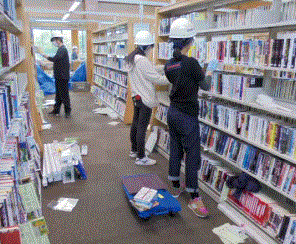
棚を紐でくくる作業を繰り返し行った
―そうして皆さんの苦労の甲斐あって5月2日には仮オープンまでこぎつけることができました。
こういった災害のとき、図書館がどのタイミングで再開するかというのは大変難しい判断だと思います 。公共施設ですから、開館するからには利用者の安全確保は当然です 。それと同様に、開館準備作業中は職員の安全が最優先です 。開館準備を急ぐあまり、職員に無理を強いるわけにはいきません 。5月2日には仮オープンしましたが、最初は児童書コーナーと臨時設置した新聞コーナーだけに絞りました 。児童書コーナーを優先させたのは、皆さん大変な思いをしている中、必要なのは“癒し”だと思ったからです 。子どもさんはもちろん、親御さんたちも子どもさんと一緒になって絵本に触れることで、心の癒しに繋がります 。また、利用者の皆さんへの情報提供も図書館の重要な役割ですので、新聞コーナーを手前の方に移動させて、臨時設置の状態で提供しました 。
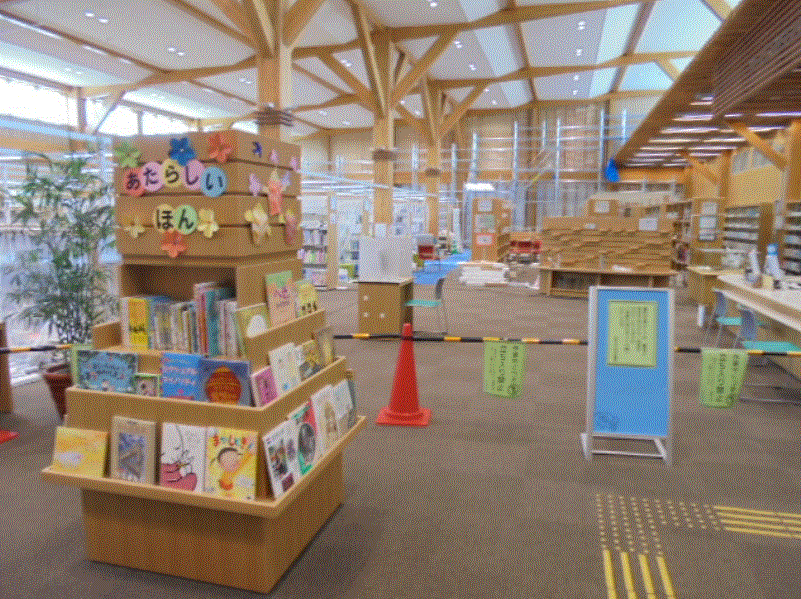
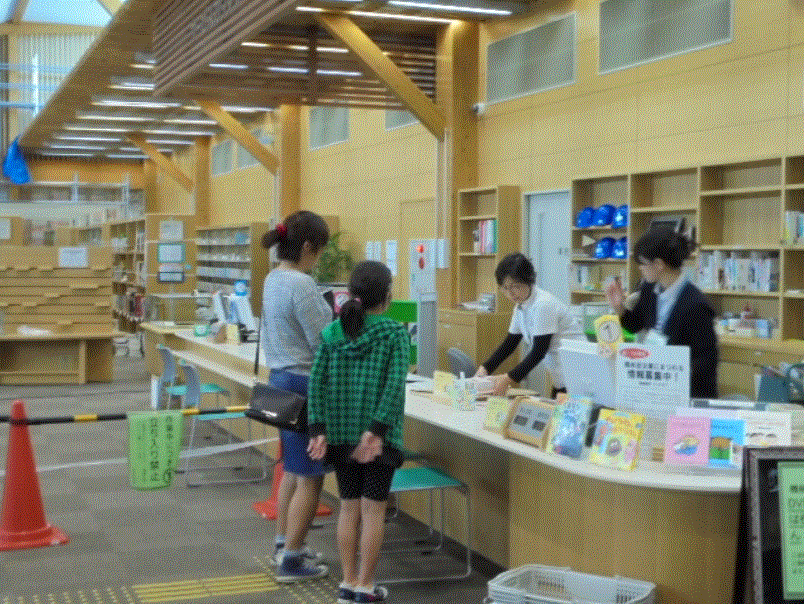
―利用者の方の反応はいかがでしたか。
新聞はよく利用されていました 。5月2日からは夜8時まで開館していたのですが、近くの避難所の方が親子連れで夕方6時過ぎに図書館に立ち寄って、ここで時間を過ごして帰っていくという姿も見られました 。避難所には多くの方がいましたので、ひと時の気晴らしの場として活用していただいていたようです 。
―その後、順次開放範囲を広げていったわけですね。
被害が少なく、復旧ができたエリアから順次開放していきました 。日を追うごとに利用者層も多様化していきましたので、段階的に提供を拡大していったエリアと、利用者のニーズがうまくかみ合ったと思います 。
―城南図書館でもう一つ特徴的だったのは、発災当初からSNSで作業の状況を公開していたことでした。
普段から情報発信は意識的に行うようにしていました 。隣接する避難所は14日の前震直後から断水の影響でトイレが使えなくなっていました 。たまたまこちらのトイレが中水利用で断水の影響がなかったのでトイレの利用開放をして、その情報をSNSで発信していました 。しかし16日未明の本震でそれもできなくなってしまいました 。近くに住んでいた職員がいましたので、16日の朝に状況を確認して、すぐにトイレ利用開放中止の情報を更新してくれました 。SNSを担当する職員は3~4名いましたので、それ以降も適宜上げられる人が復旧作業の状況を更新し、利用者に向けた情報発信を続けました 。被害の状況ばかりを上げすぎると、利用者の不安を煽ることになるのではないかという多少の迷いはありましたが、今後の注意喚起にもなることなので、結果的には良かったと思います 。
―今回の地震を受けて、今後、図書館として意識していこうと思うことはありますか。
図書館は図書館としての機能を果たしていく 。これが基本です 。奇をてらう必要はありません 。当館の職員は日常の業務をまじめに淡々とやりながら図書館職員としての経験を積み上げ、力を蓄えています 。今回、その蓄積があったからこそ、災害復旧という非常時においても、みんなやるべきことをきちんと理解して、自主的な判断のもとに的確に動くことができました 。常々、利用者の方々には、図書館は「場所」・「資料」・「人」を使う場だと申し上げています 。「人」とは職員です 。図書館職員として十分なレファレンス力をもって利用者にサービスを提供できる実力があれば、どんな時でも力を発揮できます 。散乱した本の復旧作業のやり方にしても、SNSで発信する情報の取捨選択にしても、それぞれの職員がプロとしての判断力を備えているからこそ任せることができました 。今回の経験を経て「地震に強い図書館です」などと申し上げるつもりはありません 。ただ、図書館としてやるべきことをやる 。それだけです 。
―本日は貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。
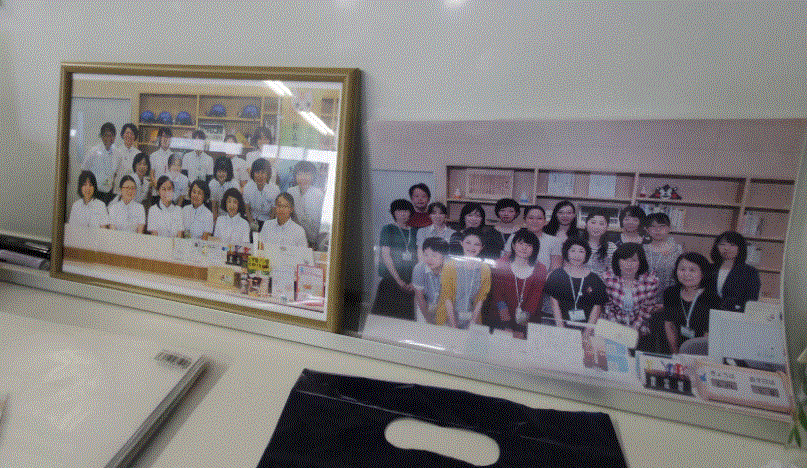
取材日:2016年8月10日